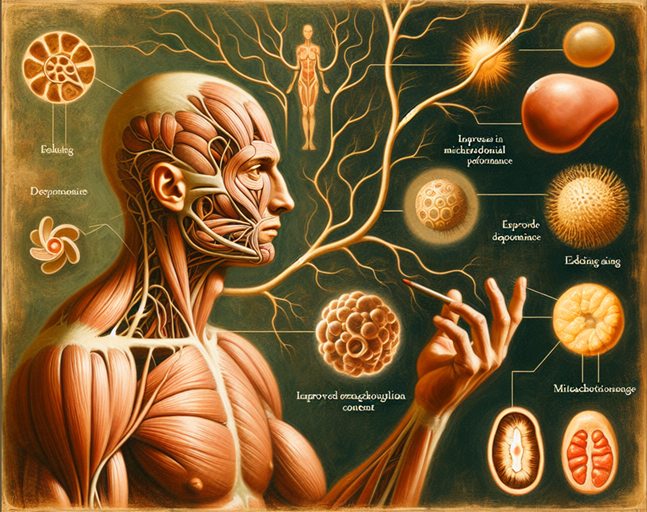認知症の発見は、ドイツの精神科医アルツハイマー博士が、51歳の女性の症例を発表した1906年に遡ります。彼女の死後、アルツハイマー博士は脳の解剖を行い、新しく開発された染色技術を使って2つの重要な発見をしました。一つは脳内に、現在アミロイドβとして知られている異常なタンパク質の塊ができることで、もう一つは、タウと呼ばれる神経線維の絡み合った束です。
アルツハイマー博士の発表は、同僚の医師たちからほとんど注目されませんでした。アルツハイマー博士の発見の重要性が認識されたのは、それから数年後のことでした。アルツハイマー博士の同僚で著名な精神科医が精神医学の教科書の中で「アルツハイマー病」を収録して、その名が定着しました。
その後もアルツハイマー博士は研究を続けましたが、1915年に51歳の若さで亡くなりました。アルツハイマー病は1960年代になってから、認知症の主な原因と考えられるようになり、1世紀以上経過した現在でも、アルツハイマー博士の研究が基礎となっています。 アミロイドβやタウなどの異常なタンパク質の沈着が神経細胞の損傷や認知機能低下の重要な原因であると現在も考えられています。
しかしアミロイド仮説に基づく臨床試験は、失敗の連続でした。これにより、アミロイド仮説の妥当性についてかなりの議論が巻き起こりました。失敗の原因は、病気の進行を抑えることができず、副作用や毒性の問題を解決できなかったことでした。そして病気が進行してからでは効果がないのではないかと考えられ始めました。
ある遺伝子変異があると、アミロイドβの蓄積やタウの凝集を形成することがわかってきました。しかしアミロイドβの蓄積は、必ずしも認知機能低下の重症度と直接相関するわけではありません。アルツハイマー病に関連する遺伝子はたくさん発見されており、混迷の度合いが増しています
アルツハイマー病の死後分析で、あることが明らかになりました。アミロイドβとタウタンパク質の周囲に炎症が起こっていたのです。実は、脳内のニューロン以外のグリア細胞に異変があることは1907年のアルツハイマー博士の論文ですでに指摘されていました。アルツハイマー博士が長生きしていれば、今と違った展開になっていたかもしれません。